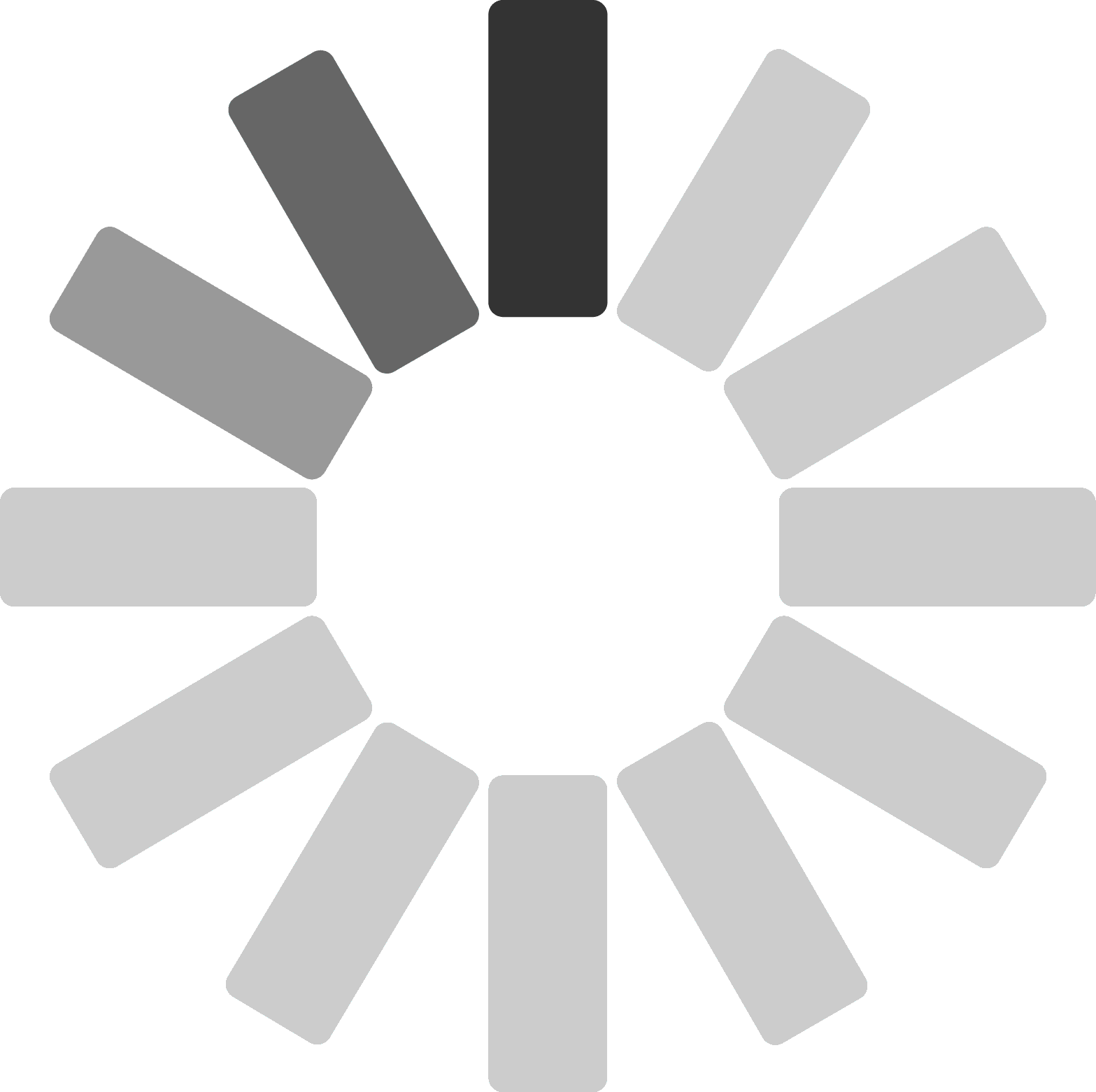「学習障害(LD)の周辺の子」といわれた娘も、ちゃんと自立した社会人になれました。
¥1,537(税込)
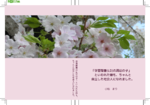
商品説明
「はじめに」 からの抜粋:
私たちの家族には療育手帳を持つ、37歳の娘がいます(2019年10月現在)。今の会社に2004年に採用されて以来、同じ職場で働いています。生活面では、2005年に東京都立知的障害者通勤寮に入寮して以来、親元を離れて暮らし、現在はグループホームで生活しています。決して平坦な道のりではありませんでしたが、今の娘を見ると、「持てる才能を最大限いかして生きていてエライ!」とつくづくと感じます。
娘が健常児ではないことを認識したのは、彼女が中学一年の終わり頃です。
「『学習障害の周辺の子』であると思われます」といわれたのが始まりでした。
本書の原稿は、2010年に書いたものです。
「大人になって自立して明るく生活している『先輩』(娘)がいることを、世の中に発信して、現在、発達障害児を抱えて悩んでいる親御さんに、勇気と希望を与えましょう」と、娘の子育て手記を書くことを勧めてくれた出版業界の知人がいたのがきっかけでした。
しかし、原稿が仕上がった時期に東日本大震災が起こり、こうしたテーマの本を出す機運は一気にしぼみ、更にその数年後に、夫が死去し、私自身が人生の岐路に立たされ、原稿は眠ったままになってしまいました。
***************
目次より[抜粋]
序章 事件:生い立ちを書きはじめる前に
第一章 健常児だと思っていた時代
1.出産
2.バンコク時代 [1歳2ヵ月~4歳]
「外国で育てているから遅れているのかも」
《家族のバンコク》 子どもの生活空間
日本語とくりかえし性癖
3.ジュネーブ時代 [4~6歳]
《家族のジュネーブ》タネー村での生活
「ちょっと変、にぶすぎる」
4.区立小学校に通った五年間
「ゆっくりとでもいい、遅れを取り戻したい」
「もう、お手上げです」
養護学校でもない、普通学級でもない
娘を受け入れ、育ててくださった方々
5.ソウル時代 [小学5年~中学一年]
能力の限界を感じる
《家族のソウル》1994年頃の韓国
母親の最大の危機と転機
第二章 LDの周辺の子を育てる
1.フリースクール飛翔時代[中学2年~3年]
学校ではないフリースクール
「私でもわかる!」ほんとうの学習
「LDの周辺の子」の親になる
IQの数値という厳しい現実
情報を追い求めて、そしてその意義
2.白根開善学校時代[高校1年~卒業まで]
運命の学校との出会い
事件: 父親の転機
父と母が育てられた三年間
3.療育手帳の取得
療育手帳を取得した理由
初めての就労相談
4.ワシントン時代[高校卒業~二十歳まで]
懐の深いアメリカの方々に支えられて
病院ボランティアの一員になる
教会での英会話教室
第三章 自立をめざして
1.帰国から就労までの道のり
第一回職場実習ージョブコーチとともにー
ついに就労先が決まる!
2.障害基礎年金の取得
申請の理由
「初めて医師の診療を受けた日」
診断書と申立書
3.親元を離れて生活する
都立知的障害者通勤寮ー自立への第一歩
初めてのグループホーム2007年5月~10月
地元のグループホームへ2007年10月~
第四章 障害者として自立して生きてゆくということ
1.「LDの周辺の子」を育ててみて思ったこと
”放っておかれた”子ども”忘れられた”子ども
療育手帳をとるかどうかは親の判断
療育手帳をとらないと公的な支援は受けられない
2.親としてめざしてきたこと、今後ともめざしたいこと
3.母のひとりごと
おわりに
著者名
小松 まり
関連URL
https://bistrotkenwood.hatenablog.com/
書籍情報
製本サイズ:B6
ページ数:230
表紙加工:カラー
本文カラー:モノクロ
綴じ方:無線綴じ